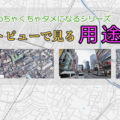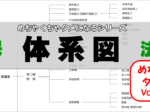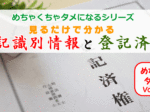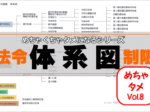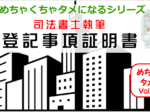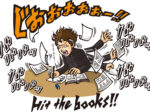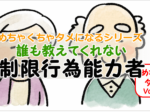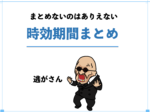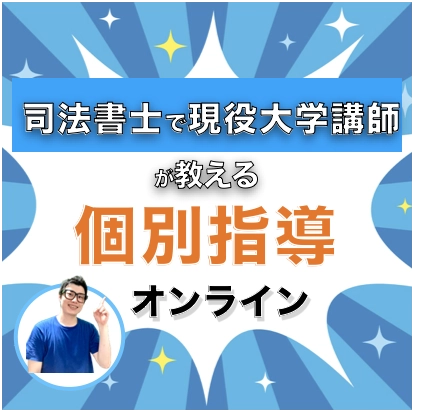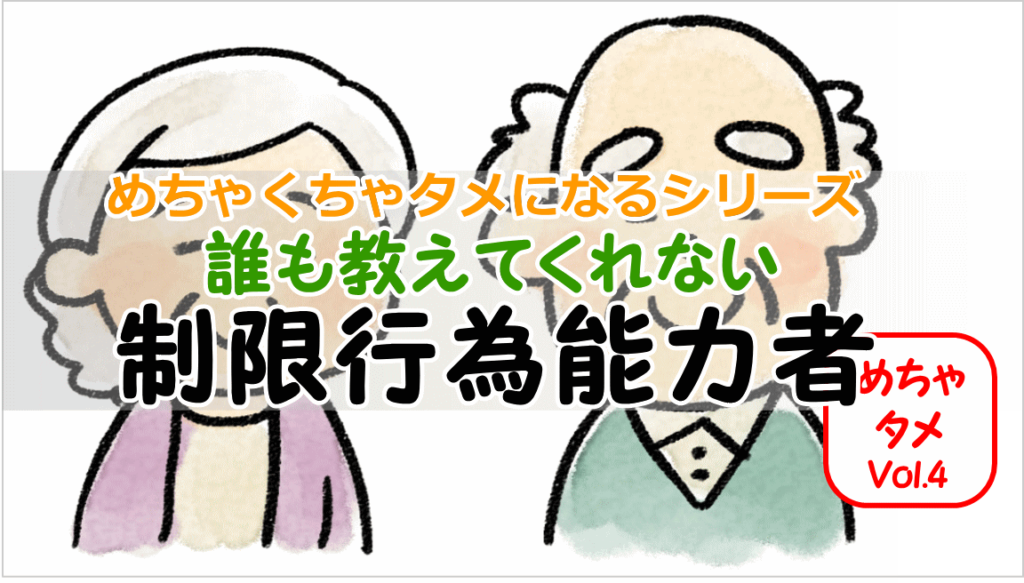
めちゃくちゃ為になる 誰も教えてくれない制限行為能力者制度(成年後見制度)
目次
読み終える時間:約5分
宅建試験のテキストには載ってないけどめちゃくちゃタメになること<!!めちゃタメの第4回目です。
この記事では司法書士が制限行為能力者(成年後見制度)の実例とデータをご紹介します。
より身近により具体的にこの記事を見るだけでイメージが沸いてくるはずです。
※制限行為能力者とは、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人のことですが、この記事では成年後見制度の説明を趣旨にしているため未成年者を含めていません。
※成年後見制度とは、成年被後見人・被補助人・被保佐人を対象にしている制度です。
※「後見」は「成年後見」のことです。実務では二文字に略して使われます。![]()
制限行為能力者のまとめ
学習した方もそうでない方も今一度、制限行為能力者を簡単にまとめておきますのでおさらいしてください。
語弊を恐れず言葉を選ばずに言えば「完全にボケている→成年被後見人」「結構ボケている→被保佐人」、「少しだけボケている→被補助人」といったイメージです。
| 後見 | 保佐 | 補助 | |
|---|---|---|---|
| 対象となる方 | 判断能力を欠いている方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
| 申立てをすることがで きる人 |
本人、配偶者、4親等内の親族、検察官等 | ||
| 保護者の同意が必要な行為 | ー | 民法 13 条 1 項所定の行為 | 民法 13条 1 項所定の行為の一部で家庭裁判所が審判で定める |
| 成年後見人等に与えら れる代理権の範囲 |
財産に関するすべての法律行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める |
成年後見制度の種類
成年後見制度は大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
法定後見制度
法定後見制度は宅建試験ではお馴染みの「後見」「保佐」「補助」に分かれていて、判断能力の程度によりいずれかの制度を選べるようになっています。上記表はこの法定後見制度を表にしたものです。
任意後見制度
任意後見制度は宅建試験では全く馴染みがありません。本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
リンク:法務省のQ.15
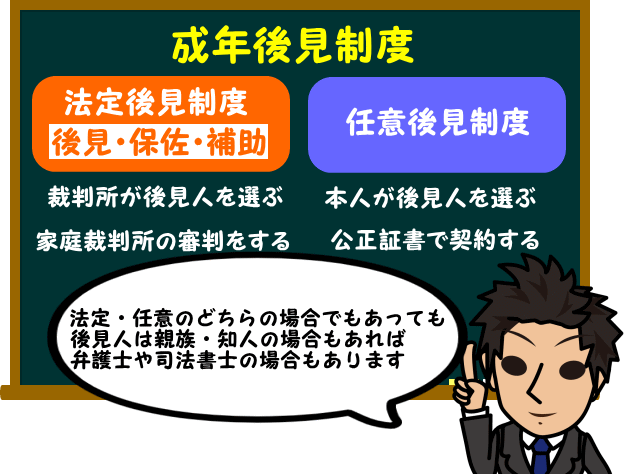
成年後見制度のデータ
少し古いデータになりますが、公開されている中で最新の情報を使って成年後見制度の数字を見ていきましょう。![]()
利用者数の推移
宅建試験でも後見・保佐・補助について学習をしますが、よく出題されるのは後見です。
それはたまたまそうなっているわけではなく、現実社会でも後見の利用者が圧倒的に多いからです。
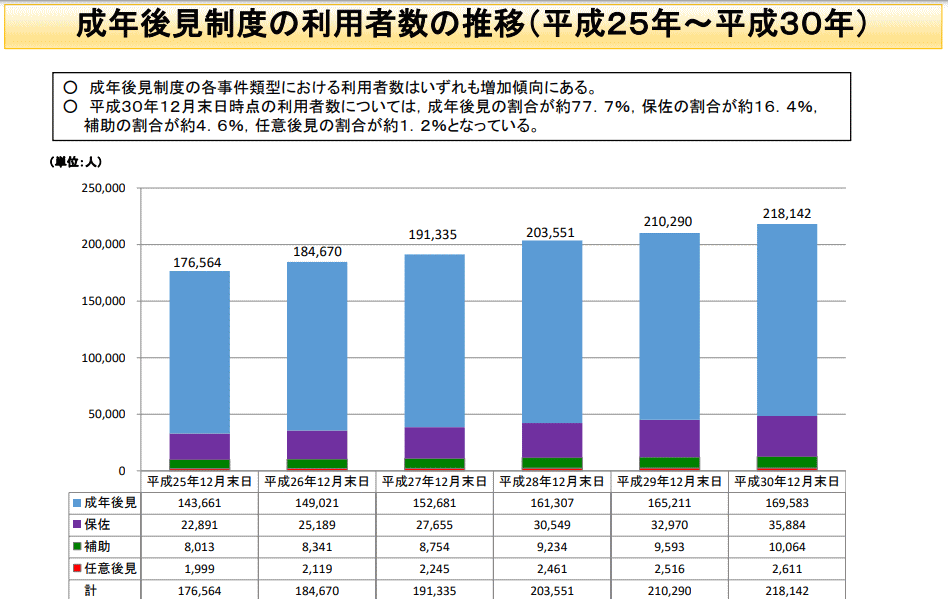
リンク:成年後見制度の現状
保佐・補助が少ない理由ですが、後見は法律構成が比較的分かりやすいものですが、同意権・代理権等のオプション設計が必要(民法13条1項など)な保佐・補助では使い勝手が悪いためです。
また、判断能力を欠く状態に至っていないのであれば、あえて制度の利用をする必要がないと心理的ブレーキがかかるのかもしれません。
申立人
申立人人は近親者や親族の割合が多いのは当然ですが、意外に市区町村長も多いです。
宅建試験的には細かい部分として聞いてきそうな検察官はなんと0です。
確かに実務で検察官が申し立てるなんていうのは聞いたことがありません。
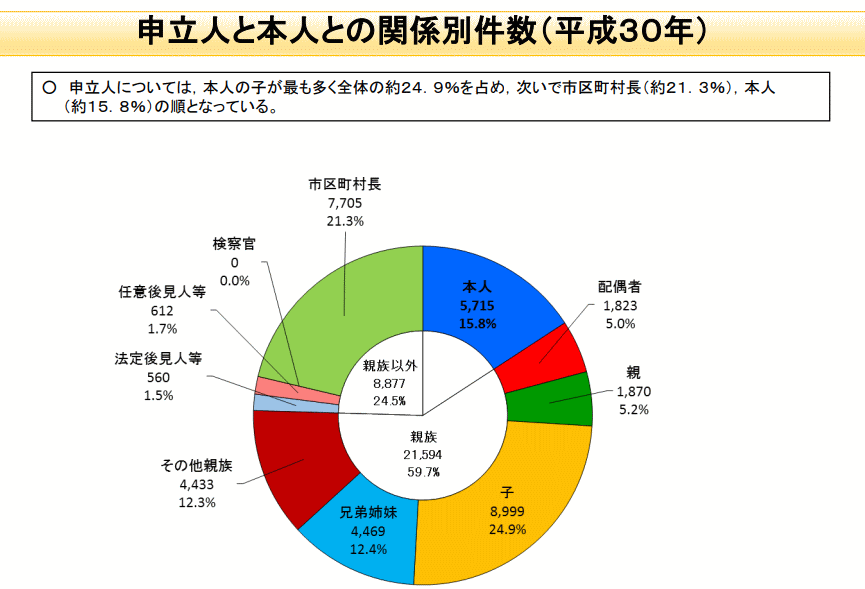
リンク:成年後見制度の現状
検察官が色々な規定で申立人になっている大きな理由は「公共性」があるからです。
後見の申立てに公共性はあると法学的には考えますが、現実的にはないのでこういったデータになっていると推測します。
【余談】他の事例
例えば、不在者財産管理人の制度(参考:wiki)を見てみると不在者財産管理人の請求権者に検察官は含まれています。
これは、管理者がいない財産は、管理や処分が出来ず荒廃が進んでしまうという問題があるからです(最近では空き家対策も活発になってきましたよね)。よって、不在者財産管理人の申立てをすることは国民全員に対しての公共性があります。
それに対して、失踪宣告の制度(参考:wiki)には失踪宣告の請求権者に検察官は含まれません。
これは、親族が帰りを待っている中、検察官が勝手に死亡したことにするのは親族の意思に反するだろうということです。つまり公共性がありません。![]()
本人の男女別・年齢別割合
年齢別で見てみるとまず20歳未満が0.2~0.3%です。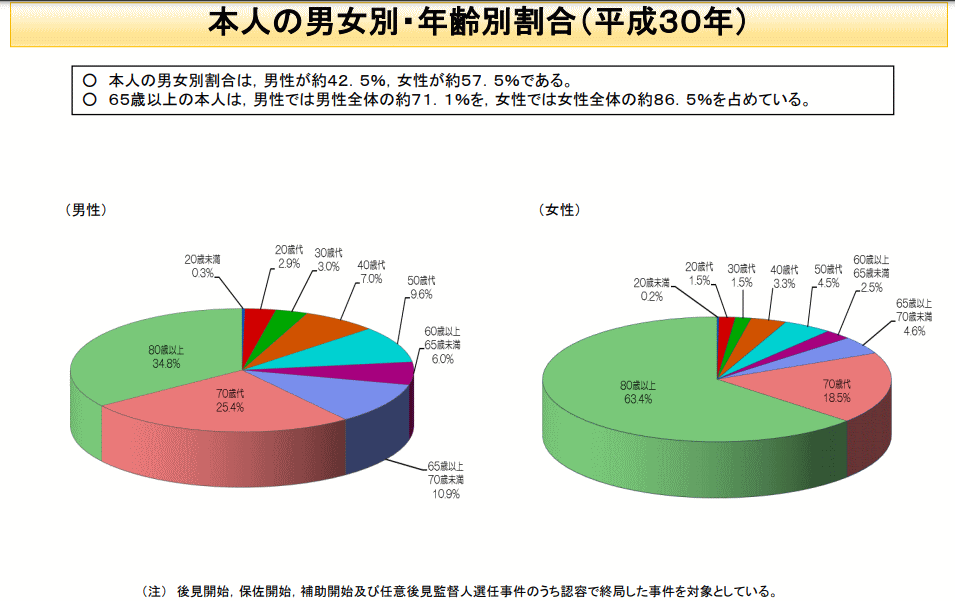
リンク:成年後見制度の現状
宅建試験的な知識でいえば、未成年者でも成年被後見人になることができます(未成年者なのに”成年”被後見人になれるって言葉がややこしい!(~_~メ))。
たとえば、平成26年 問9-3では以下のように出題されています。
宅建試験 H26-9-3
未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。
答えは誤りです。
理由はwikiにも載っているんですが「未成年者の知的障害者が成年に達する場合には法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)がいなくなってしまうことから、その時に備えて申請を行う必要がある場合もあるため後見開始の審判の対象には未成年者も含まれる」ということです。
反対に、多い方に目を向ければやはり70歳~だけで半数以上を占めていますね。
これは判断能力が低下した人の法的支援という後見制度の趣旨と一致しています。
費用
成年後見制度はもちろんタダでは利用できません。
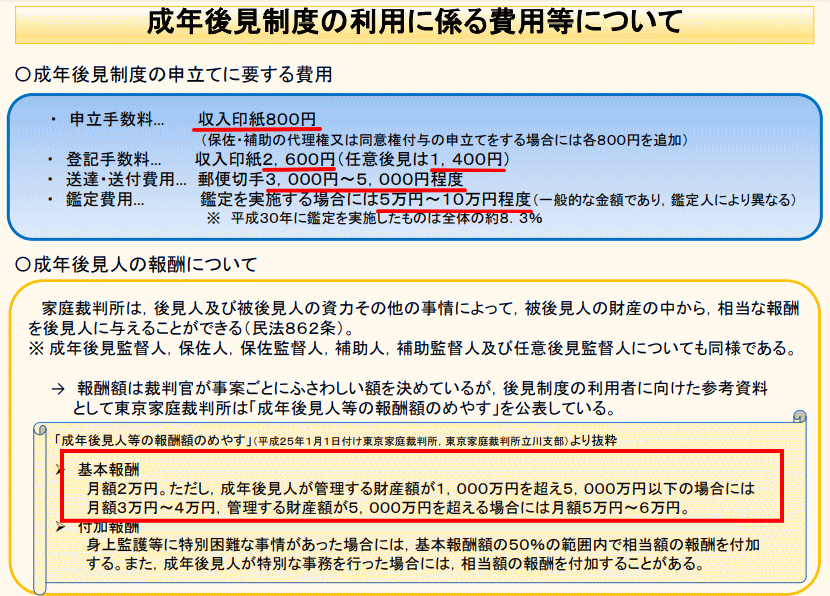
リンク:成年後見制度の現状
申立てるに当たって鑑定なしなら総額8000円~10000円程度といったところです。鑑定ありならプラス5~10万円程度ですね。
成年後見人への報酬は毎月発生します。
これは司法書士などが後見人になる場合に発生するもので、私の司法書士仲間には20人ほどの成年後見人になっている方もいます。
後見人の職業
子供や親戚など親族が後見人になる場合もありますが、意外と親族以外のほうが多いことはご存知でしょうか。
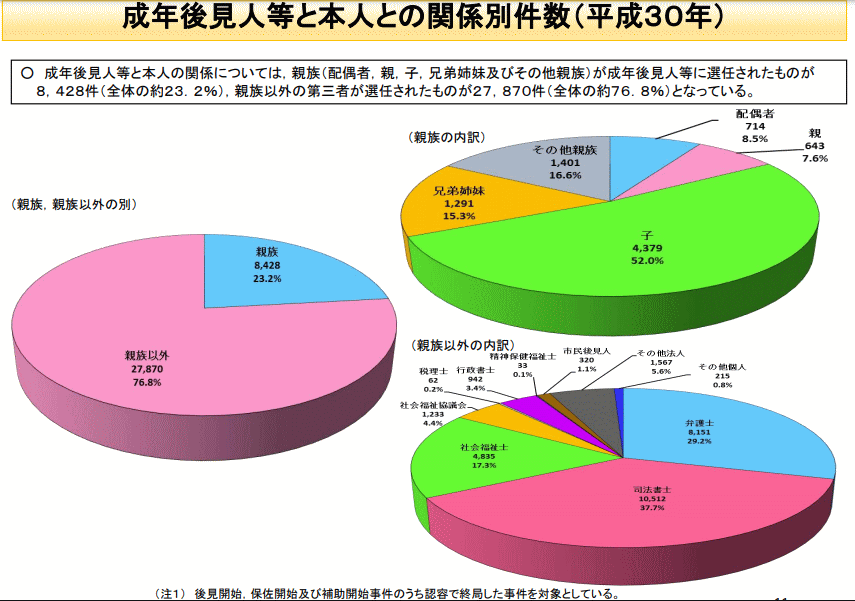
リンク:成年後見制度の現状
親族であれば子が多く、親族以外であれば司法書士が後見人になることが多いです。
親族以外へ頼むのは、そもそも親族がいない場合もありますし、親族がいてもその負担を考えれば親族以外に頼んだほうが良いということもあるからです。
また、親族であれば勝手に財産を使い込むこともあります。親族以外でも横領事件になることはありますが(-.-;)ほんとけしからん。
なお、司法書士等であれば後見人の仕事が突然舞い込んでくるわけではありません。
司法書士等であっても公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートで後見人になるための研修や登録が必要です。![]()
後見人の仕事
後見人は身体のサポートをするわけではありません。
財産についての管理をします。
例えば以下画像のように成年被後見人のために使ったお金のレシートを台紙やノートに貼り付けて管理をします。
そして、これを定期的に裁判所へ報告します。
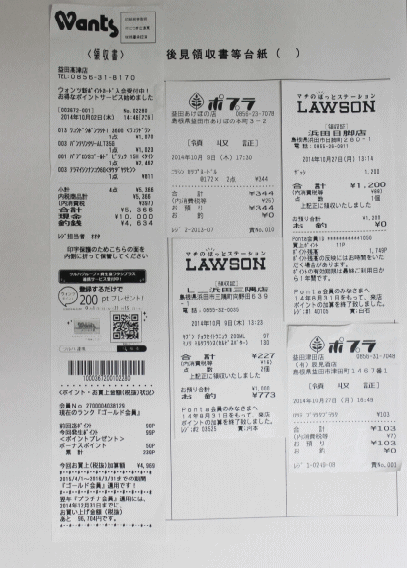
リンク:田上法律事務所様
まとめ
制限行為能力者(成年後見)の制度の教科書だけを見ていては決して見えないことを記事にしてみました。
机上の勉強だけではなく、制度そのものを知ることによって試験にもその知識は生きてくると思います。
成年後見の申立てはお近くの家庭裁判所へご相談ください(参考:東京家庭裁判所後見センター)。
この記事が役に立ちましたら宅建部のツイッターをフォローして頂ければ励みになります。
ありがとうございます。それでは失礼します。